KANBINAについて
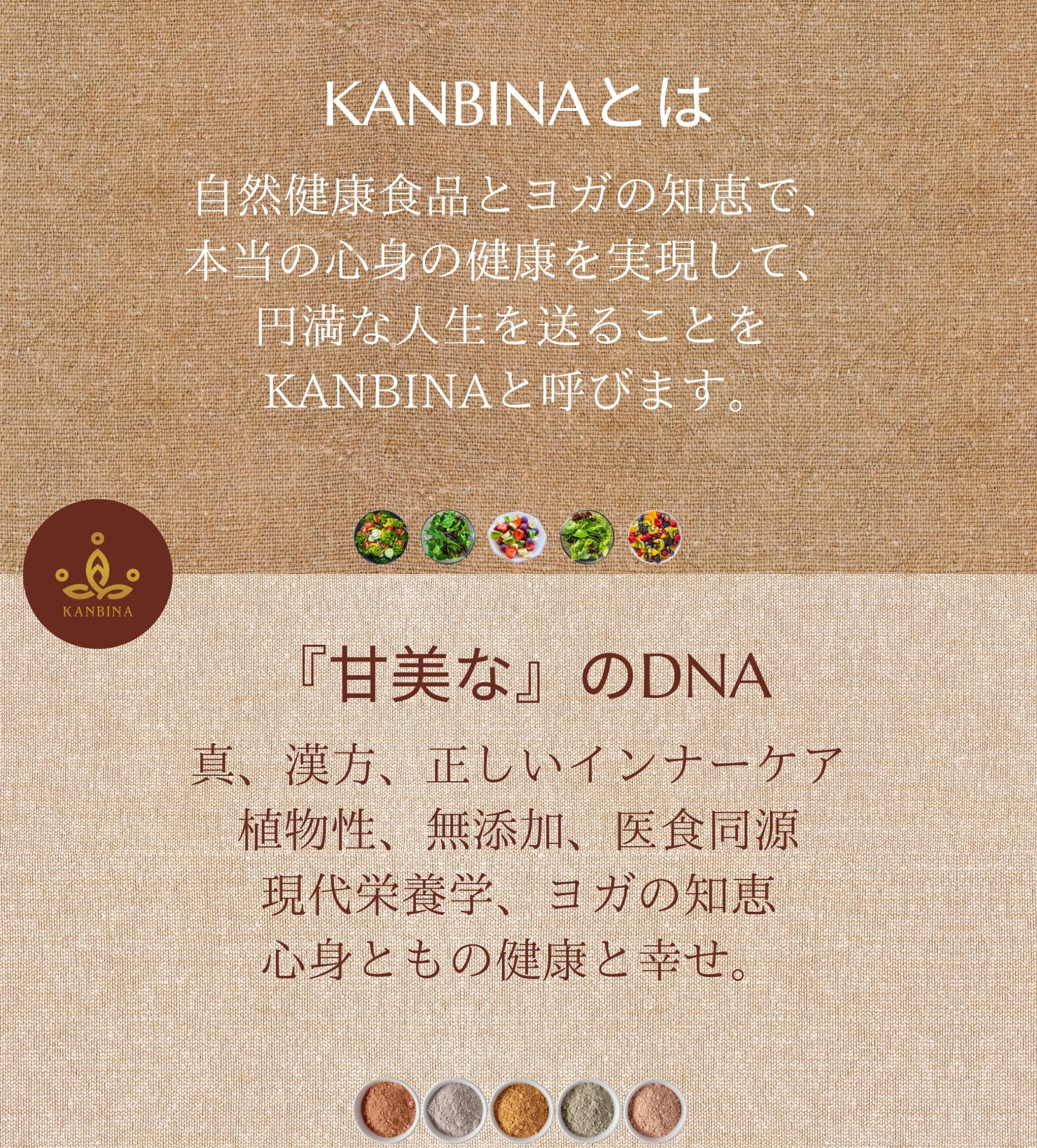
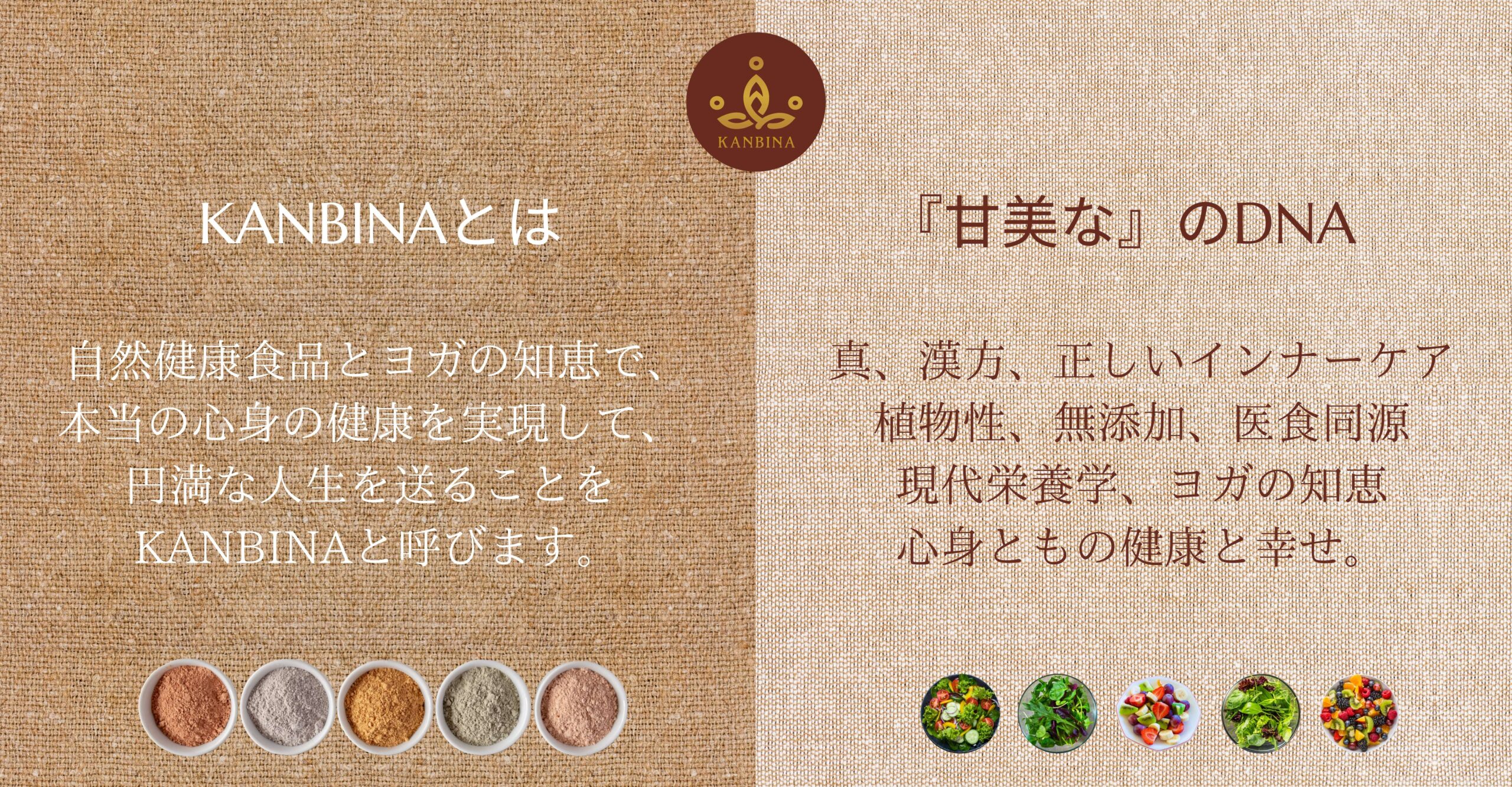
KANBINAブランドストーリー
「健やかな未来へ、自然の恵みを。」
健康に暮らし、いつまでも美しく過ごすことは、誰もが願う永遠のテーマです。
そのための第一歩は、やはり 「食」。
しかし現代社会では、多くの食品が効率や経済性を優先し、
添加物や過剰な糖分・塩分に頼っています。
忙しい生活の中で、私たちは知らず知らず“自分に合わない食”を選びがちです。
KANBINAが目指すもの
KANBINAは、そんな時代に生まれた 自然健康食品ブランド。
人・社会・地球に優しい植物性素材だけを用い、
完全無添加・体質別・パーソナルケア にこだわった
食品を製造・提供しています。
古来より人々を癒してきた 薬膳とハーブの叡智 を現代に取り入れ、
「医食同源」「美容薬膳」「ヨガの教え」など、心身を整える知恵を融合。
美と健康を一人ひとりの体質に合わせて支える ―― これがKANBINAの使命です。
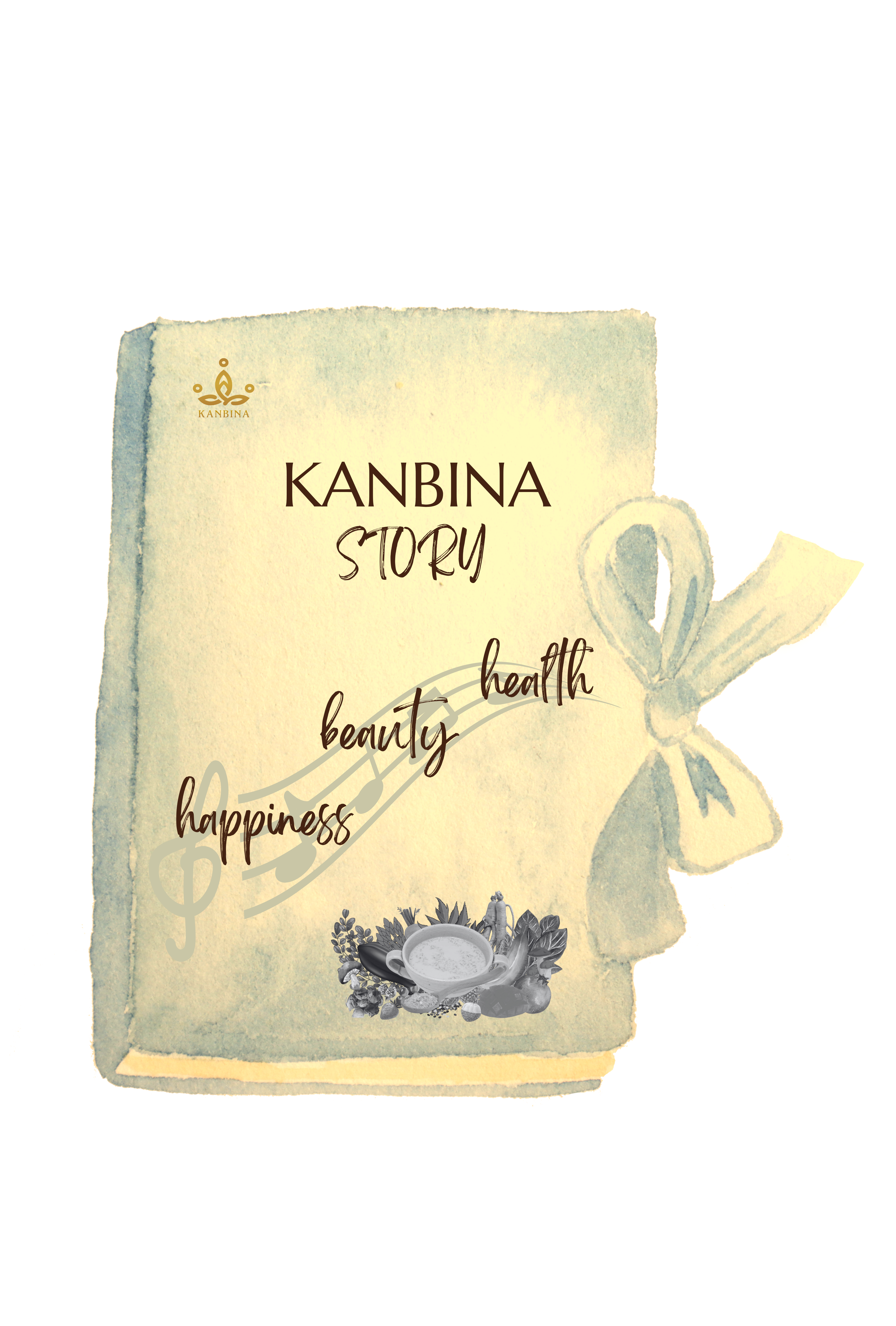
“飲むケア”という新習慣
KANBINAの製品は、ただの食事ではなく、「健やかな未来への投資」。
あなた自身の体質に寄り添い、無理なく続けられる“飲むインナーケア”です。
内側から整えることで、美しさも健康も自然に育まれていく。
「薬膳 × 無添加 × パーソナルケア」が、その毎日を支えます。
共に描く、健やかな未来
KANBINAは、身体の健康だけでなく、
心や精神のバランスも大切にしています。
サロンや法人様とともに、「本当に必要なものを自分で選ぶ」
時代の新しい価値観を広めていきたい。
一人でも多くの方に、正しいインナーケアを届けること。
それが私たちの願いです。
一緒に、健康で幸せな未来を描きませんか?
ロゴに込めた思い
KANBINAのロゴは、本当の心身の健康を実現して、「自利利他」円満な人生を送る状態を表しています。

3つの輪:
- ① 身体,心,気を象徴。
- ② 健康,美,幸福を象徴。
- ③ 見る人によって、各自の三つの願望を象徴。
本体:真我を象徴しています。
KANBINAの健康哲学
ヨガなどの適切な運動で身体を調和し、なるべく自然に近い健康な食生活で栄養と気を補充し、瞑想などで心のケアをする。
この3者の融合で本当の心身の健康を保つことができる。
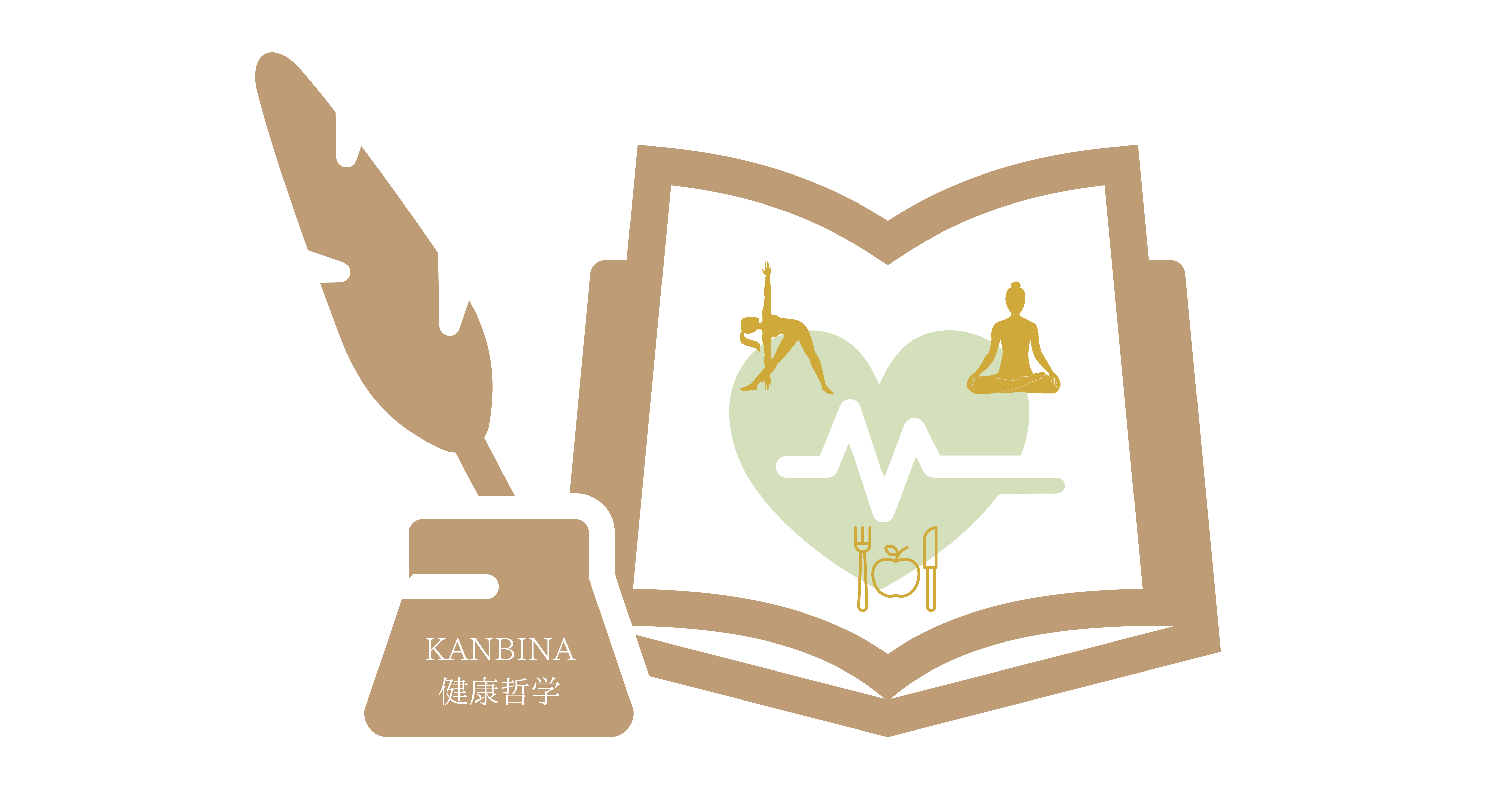
KANBINA のクレド(Credo)
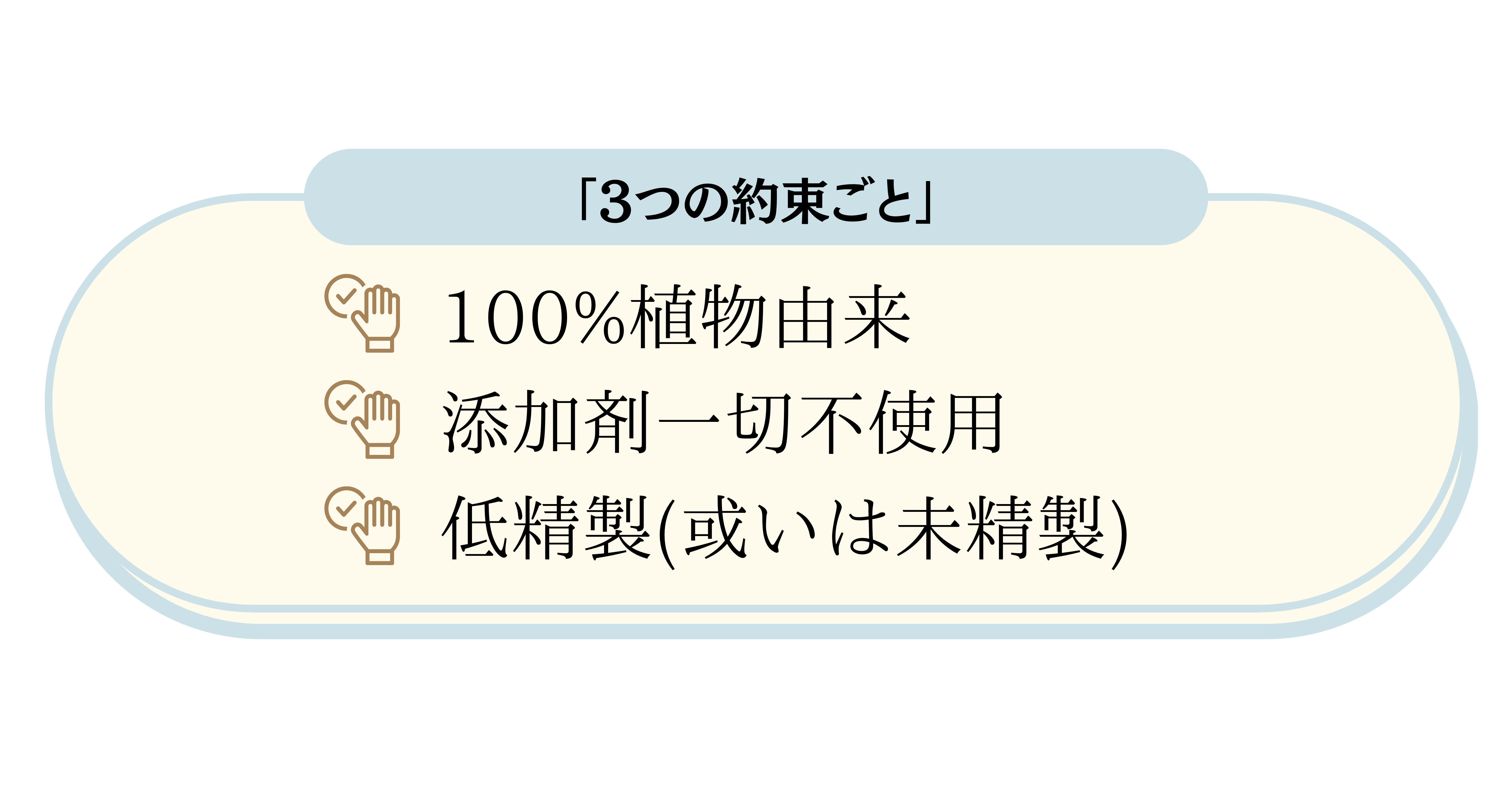
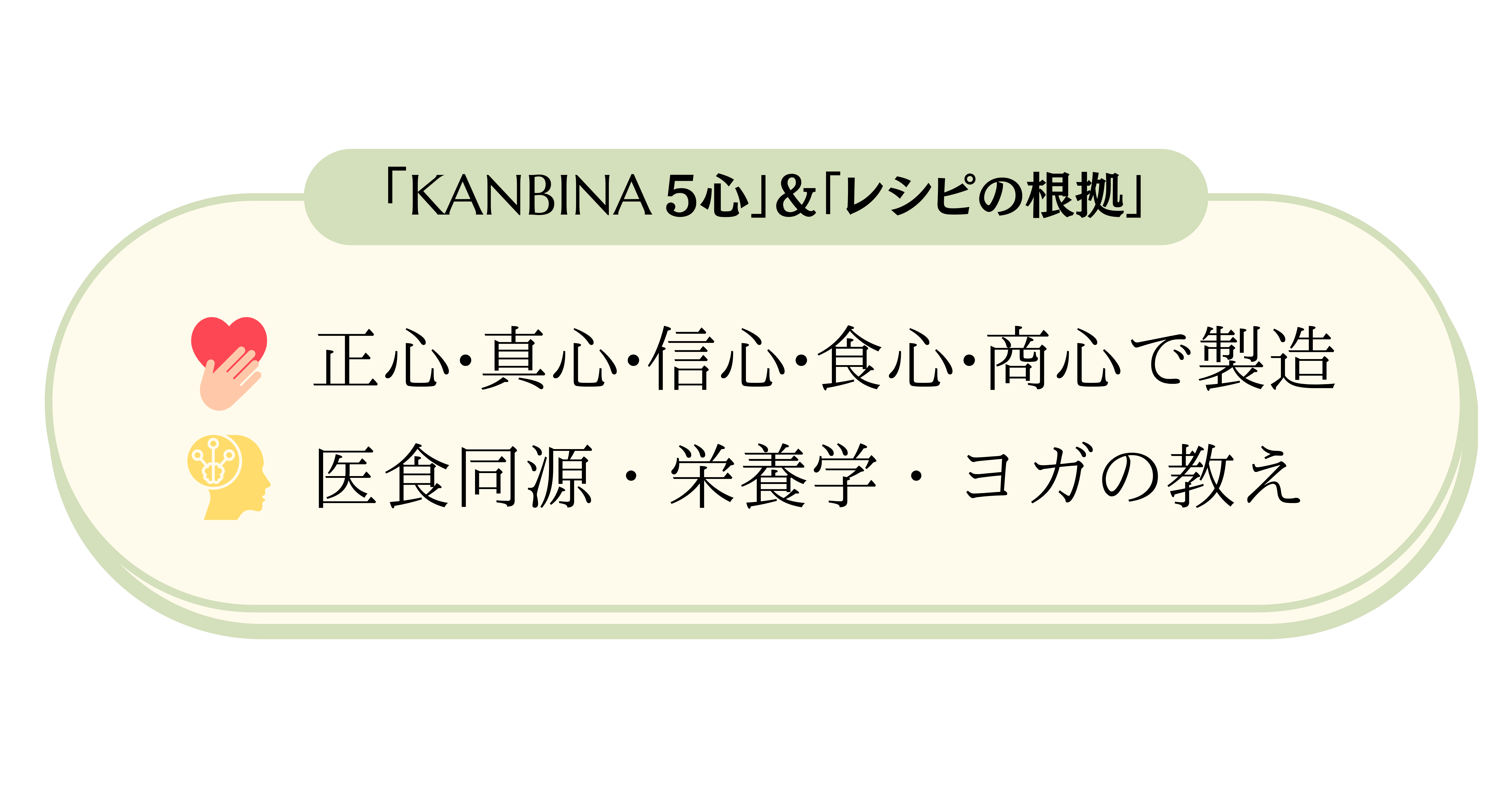
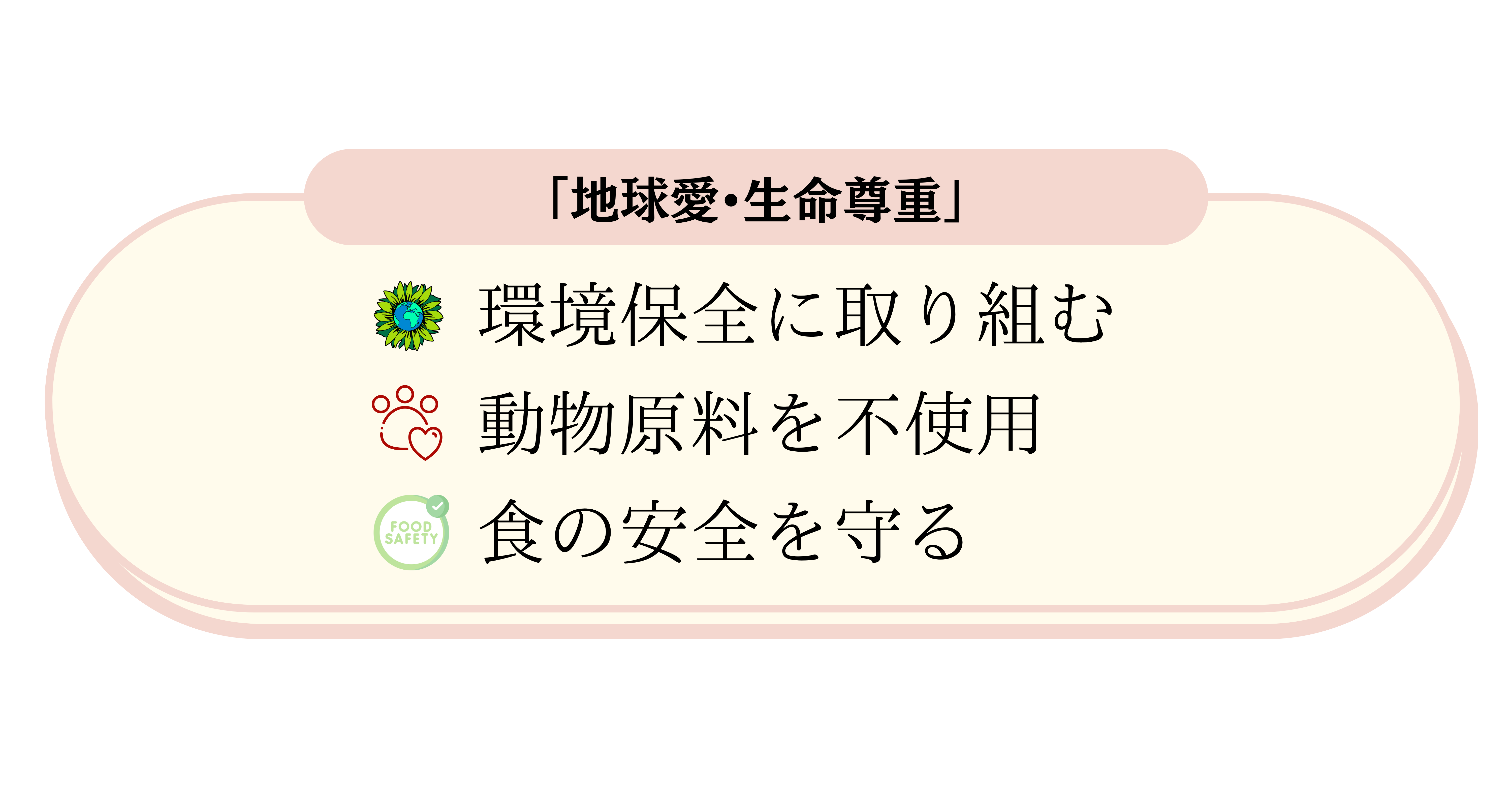
人、社会、地球の健康を考えるKANBINAは天然、植物、完全無添加にこだわります。
SDGsに積極的に取り組んで、常に環境にやさしい行動をとります。
食の安全を守り、自由平和、共同発展を提唱します。
- 環境保護
- 動物保護
- 食品安全
- 自由平和
- 共同発展
KANBINA(甘美な)ブランド紹介
KANBINA(甘美な)は日本HM株式会社の事業ブランドで、その傘下に製品ブランドがあります。
以下は全部製品ブランドです。
- YOGARO (ヨガロ)
- 美飲セブン
- 美ファスティング栄養食
- 美トックス
- 美完全食
- 食べる栄養茶
- YOGARO (ヨガロ)
- 美飲セブン
- 美ファスティング栄養食
- 美トックス
- 美完全食
- 食べる栄養茶

 オンラインストア
オンラインストア











